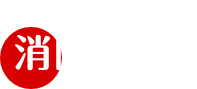企業のオフィスで、レイアウト変更に伴う誘導灯の増設工事を担当させていただきました。
「部屋を壁で仕切っただけなのに、なぜ大掛かりな工事が必要なの?」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。実は、部屋のレイアウトが変わると、火災時の避難経路も変わります。そのため、消防法の基準に従って、新しい避難経路を正しく示すための誘導灯を増設する必要があるのです。
【専門用語解説】誘導灯とは?
緑色の背景に白抜きの「走る人」マークが描かれた、おなじみのあの照明です。火災などの非常時に、避難口や避難する方向を指し示し、人々を安全な場所へ導くための重要な設備です。
今回は、この誘導灯増設工事の具体的な内容と、現場で感じた苦労話、そして工事を終えた後の達成感について、リアルな作業者目線でお届けします。
工事の舞台裏:天井裏での格闘と具体的な作業内容
「安全の光」を灯すための4ステップ
今回の工事は、新たに設置された間仕切り壁によって生まれた「廊下」や「区画された部屋」に、適切に誘導灯を増設するものでした。その作業工程は、大きく分けて以下の4ステップです。
| ステップ | 作業内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 調査・設計 | お客様からいただいた新しいレイアウト図面をもとに、どこに、どの種類の誘導灯が必要かを判断し、設置位置をマーキングします。 | 消防法の基準と、実際の人の流れ(動線)の両方を考慮して最適な位置を決めます。 |
| 2. 配線工事 | 分電盤(※)から電源を取り、誘導灯を設置する場所まで、天井裏に電気配線を通していきます。 | 天井裏の構造を把握し、最短かつ安全なルートで配線するのが腕の見せ所です。 |
| 3. 器具取付 | マーキングした位置の天井や壁に穴を開け、誘導灯本体を固定金具でしっかりと取り付けます。 | 器具が傾いたり、天井ボードを傷つけたりしないよう、細心の注意を払います。 |
| 4. 結線・点灯確認 | 通してきた配線を誘導灯の端子に接続(結線)し、正常に点灯するか、内蔵バッテリーでの非常点灯に切り替わるかを確認します。 |
【専門用語解説】
- 分電盤:ブレーカーが集まっている箱のこと。ここから各電気設備へ電気を供給します。
- 結線(けっせん): 電線の心線どうし、または心線と器具の端子とを電気的に接続することです。
正直、ここが辛かった…天井裏でのリアルな苦労話
華やかに見えるリニューアル工事ですが、その裏側には地道な苦労があります。今回、特に辛かったのは以下の2点です。
- 天井裏という名の異空間
今回の現場は、天井裏のスペースが非常に狭く、まさに「ほふく前進」での作業でした。長年積もったホコリにまみれ、照明の届かない暗闇の中、頭をぶつけないように配線ルートを探すのは、体力的にも精神的にもハードでした。特に点検口から遠い場所への配線は、本当に骨が折れる作業です。 - 「美観」という名のプレッシャー
オフィスは働く方々が毎日過ごす場所です。誘導灯の取り付け位置が少しでもズレていたり、配線を通すための穴が汚かったりすると、非常に目立ちます。機能性はもちろん、「見た目の美しさ」も同時に求められるプレッシャーは、何度経験しても慣れないものです。水平器を片手に、ミリ単位で位置を調整する作業は、非常に神経を使いました。
工事を終えて:得られた達成感と安全な空間の創造
苦労の先に見えた「改善」とお客様の安心
そんな苦労の末、無事に工事は完了。薄暗く、どちらへ逃げればよいか分かりにくかった新しい廊下に、緑色の光が灯りました。
- 目に見える改善
どこが避難口で、どちらへ進めば良いかが一目瞭然になりました。暗闇の中でもはっきりと認識できる誘導灯の光は、まさに「安全の道しるべ」です。 - 法令遵守による安心感
今回の工事により、オフィスは完全に消防法に適合した状態となりました。万が一の際に法的な不備がないという事実は、企業様にとっても、そこで働く従業員の皆様にとっても、大きな安心材料になったと思います。
完了報告の際に、お客様から「これで新しいレイアウトでも安心して仕事ができます。綺麗に仕上げてくれてありがとう」と声をかけていただけた時、天井裏での苦労が報われたと心から感じました。
まとめ:デザイン性と安全性の両立のために
今回は、間仕切り変更に伴う誘導灯増設工事の裏側をご紹介しました。
オフィスのレイアウト変更は、働く環境をより良くするための素晴らしい取り組みです。しかしその際、利便性やデザイン性だけでなく、「万が一の時の安全性」も忘れてはなりません。
私たちの地道な作業が、皆様の働く空間の安全を支えている。その誇りを胸に、これからも一つひとつの工事に真摯に向き合っていきたいと、改めて感じた現場でした。
工事前

工事後